〒223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉2丁目12-7 オーシャンハイツ1階2号室
(日吉駅から徒歩6分)
受付時間
定休日:月曜日
自費リハビリお役立ち情報
~麻痺した手を使えるようになるためには~

麻痺した手を使えるようになりたいと思っていませんか?
脳卒中(脳梗塞・脳出血・クモ膜下出血)や脊髄の病気になると腕や手を自由に使うことができなくなります。全く動かなくなる”完全麻痺”の場合もありますし、動くけども不自由という”不全麻痺”の状態になる場合もあります。また、「動くけどしびれている」とか、「細かいことができない」という訴えもよく聞かれます。
脳卒中になったあと、多くの場合は、歩けるようになることが第1目標となります。手も動かないのですが、麻痺していない側の手を使って何とか生活ができることもあるため、優先順位が下がってしまうのかもしれません。
リハビリを頑張って、「何とか歩けるようになったけど、腕が曲がってきて困ります。」という訴えを聞くことがありますが、その時点から改善するのはなかなか大変なのです。
ここでは、麻痺した手を使えるようになる方法をお伝えします。
麻痺した手のリハビリを困難にしている3つの誤解
- 医師に「動くようになりません」と言われた
- 足と腕のリハビリを別々にやっている
- 歩くときに手がぶらぶらしないように布で吊っている

脳卒中になって、数日で医師に「この手は動くようになりません。」と言われたと聞いたことがあります。もちろん、主治医次第ですが、その背景には、最悪の場合を伝えている、画像診断上回復しない可能性が高い、一般的なリハビリの経過(エビデンス)に従っている、ことなどが考えられます。医師の立場とすればそれは適切な対応と理解もできます。しかし、我々療法士はそう言われた方の手が動くようになった経験をたくさん持っています。
リハビリで足は”足の先生”、手は”手の先生”となっていませんか?または、手は作業療法士の先生がやるものだと思っていませんか?
現在のリハビリテーションの枠組みではその傾向があるように思われますが、手と足を別々な考えでリハビリをすることは非常に効率が悪いと思われます。また、理学療法士が足と歩行練習、作業療法士が手と日常生活動作の練習と分けていることも多いかと思われます。お互いの練習内容がうまく連動していればそれでも良いのですが、そこまで熟練したチーム医療はほとんど見たことがありません。
理学療法士も作業療法士も人の体はすべてが連動していることを理解してリハビリテーションに取り組む必要があります。その中でそれぞれの専門性を活かすことができれば素晴らしい結果が得られるでしょう。
とある神経リハビリで有名な理学療法士の講演を聞いたときの話です。
ロボットを使った歩行リハビリの成果をお話しされていました。確かに麻痺側の足の筋肉がよいタイミングで収縮している結果が得られていました。そこで、私は「それだけ麻痺側の足が良くなったのですから、麻痺側の上肢(腕)にもかなり良い影響があったのでは?」と聞いたら、「上肢のことはよくわからないので専門の先生に」と回答されていました。その先生は、患者さんにしっかり向き合っているのでしょうか?脳と体のシステムを理解されていれば麻痺側の足で体重を支えることと麻痺側の腕の機能が連動していることは当然理解し、経験しているはずです。歩くことの数値だけを見ているとそうなってしまうんですね。
腕を骨折したときに腕を布で吊っているのを見かけたことがある方も多いでしょう。腕が麻痺したときに以前は同じように腕を吊っていた病院も多かったのではないでしょうか?あの形は日常生活ではあり得ない位置ですし、脳が”手は使えないもの”と錯覚してしまう要因にもなります。
このように”手は動かないもの””使えないもの”と脳が思ってしまうことが手の回復を妨げる最も大きな原因と思われます。
麻痺した手を使えるようになりたいを解決する3つの方法
- 麻痺した手をとにかく多く使う
- 手を使うイメージをする
- バランス練習・全身を使った運動をする
手を多く使う

手が使えるようになるためには使う頻度を増やす。
これは最も単純な解決方法ですが、エビデンス(根拠)のある方法です。リハビリの効果は運動量によって変わってきますので、なるべく多く使うというのは重要です。
これはある程度手が動く人に有効な方法です。手はただ動かすよりも物を使うほうが有効です。自分で手を開くことができない場合には、麻痺のない側の手を使って麻痺側の手に物を持たせても大丈夫です。一度持ったら、力を入れる練習ではなく、その物を操作するようにしてみましょう。そして、物を放す練習で力を抜くことができれば次は物に手を伸ばすことができる可能性があります。
どのような物が良いのかは、個人差がありますが、病前からよく使っていたものが良いでしょう。また、大きさ、重さ、形などを変えて持って操作してみることもよいでしょう。手が物の形に合うようになることを目指します。
同じ物であれば難易度は、物がテーブルに置いてある状態で操作すること→それを持ち上げて空間で操作する→物を移動させる→物を放してもう一度持つというように変えていくとよいでしょう。
全く手が動かない方やわずかしか動かない方には電気刺激療法や機械やロボットを使った練習方法が提案されています。機械を使用される場合には専門家に相談することをお勧めします。
手を使うイメージをする
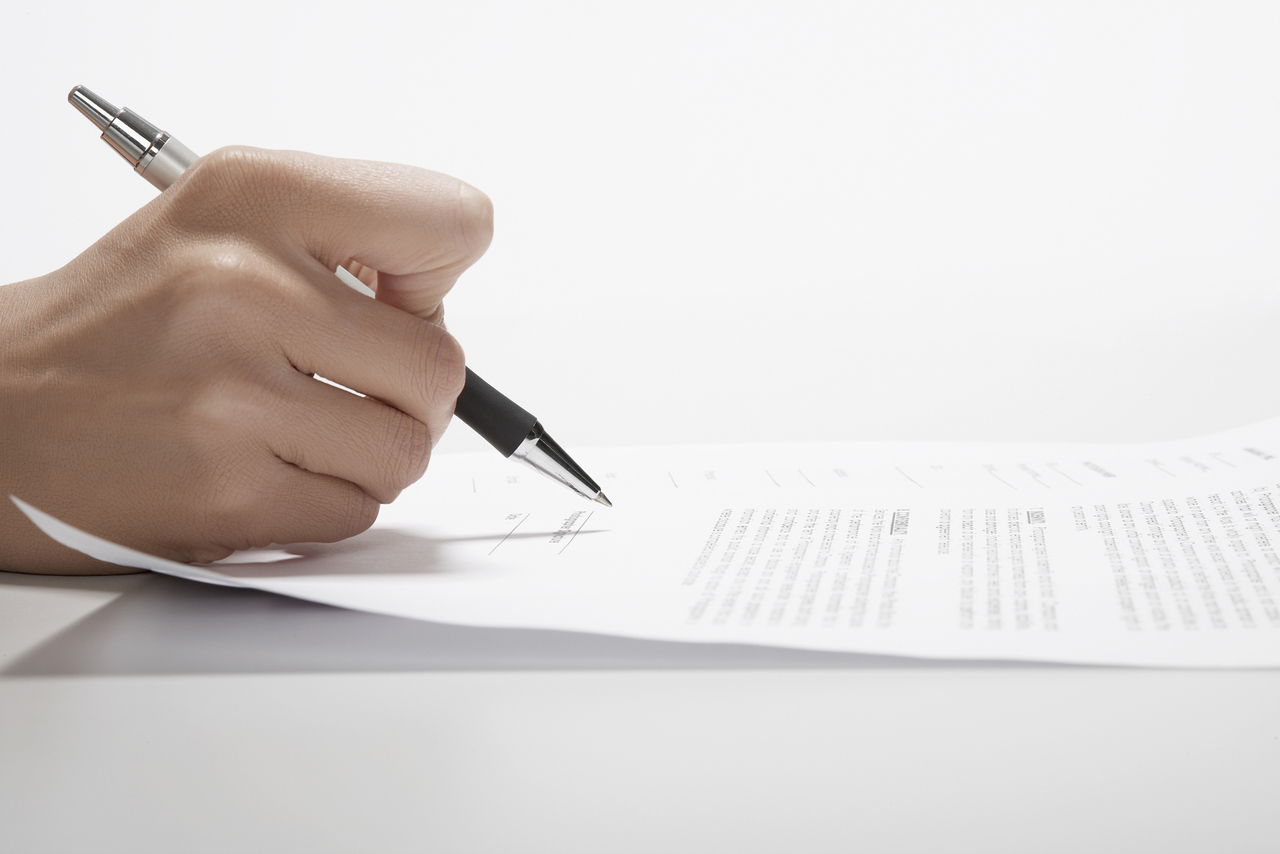
イメージトレーニングは集中力が必要で、難しい方もいらっしゃいますが、全く力が入らなくても練習することができます。
手のリハビリに限らず、基本的に人はイメージできないものは実現できません。脳のMRIの研究で一流のサッカー選手のほうがよりフェイントで相手を抜くイメージを具体的にできるという研究報告もあります。
手のリハビリで最も問題になるのは、”使わないことを学習すること”です。先に挙げた3つの誤解にあるように、脳卒中後に全く動かなくなった時に、すぐに麻痺側でない手ですべてをやり始めることや動かないと言われてそう思ってしまうこと、思っていないように手がなってしまうことなどの経験で麻痺した手を忘れてしまうことが使えなくなるとても大きな要因です。初めのうちに忘れてしまった手を取り戻すのは何倍もの時間がかかります。
そのため、手を使うイメージ(なるべく多く・具体的に物を使う)トレーニングを行うことと先に挙げたようなものを持たせて手に感覚の刺激をいれることが重要となります。
- バランス練習・全身を使った運動をする

上記の2つは手についてお伝えしましたが、手の回復を望んでいる方の多くの方に必要なのはこの練習です。
先にお伝えした通り、手と足は連動しています。手と足をつなぐ体の部分もとても重要です。腕が曲がってきてしまう人は、まず歩くことがうまくならないと腕と手の機能を回復することは難しいです。
また反対に脳が手を忘れてしまっているためにうまく歩くことができていない方も多くいらっしゃいます。
発症当初から、全身の動きが連動できるようにトレーニングをされている方は、脳が回復して手が動き始めたときにスムーズに手を使う練習が開始できます。2本の足でしっかりバランスをとることができれば、腕や手の筋肉が硬くなって動かなくなることはありません。
また、麻痺手が全く動かないままでも手をつくことができるだけで、全身に与える影響はかなり違ってきます。
このように、脳と体の動きに関してよく理解している療法士は、必要な時に必要なリハビリを提供することができます。理学療法士と作業療法士がお互いの専門性を理解して、部分的にはオーバーラップしながら治療を行えている施設は良いリハビリと言えるでしょう。
それでも麻痺した手のリハビリにお困りなら

あなたの麻痺手の悩みを解決します。
当施設では麻痺手の改善に特化したリハビリテーションサービスを提供しています。
上記の通り、麻痺した手が使えるようになるためには、バランスや全身の運動を改善する必要があります。それに加えて、麻痺した腕や手に必要なトレーニングを行う必要があります。
当施設では、姿勢やバランスの改善を基礎とした麻痺手の改善プログラムを提供しております。お客様個々の手の状況に合わせてどのようなバランス練習が必要か、手にはどのような刺激が適切かなどを専門的に分析しトレーニングすることが可能です。
発症後時間が経っている方でもあきらめるのは早いです。麻痺した手にお困りの方はぜひ一度お問い合わせください。
そのほか、ボトックス注射後や再生医療後の後療法でリハビリを行いたい方も対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
この記事について
作成日:2024年5月13日 作成者:大槻 暁
お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※月曜日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでご予約・お問い合わせができます。
S. Studio 予約・相談専用アカウント

Rehabilitation S. Studio

住所
〒223-0061
神奈川県横浜市港北区日吉2丁目12-7
オーシャンハイツ1階2号室
アクセス
日吉駅から徒歩6分
※駐車場は近隣のコインパーキングをご利用ください
受付時間
10:00~18:00
定休日
月曜日

